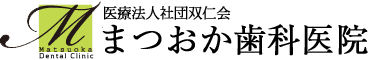かみ合わせが悪いと起こる全身の不調とその対策
こんにちは!まつおか歯科医院副院長の松岡夏紀です。「かみ合わせが悪いと、歯や顎だけでなく、全身にさまざまな不調を引き起こす可能性がある」と聞いたことはありますか?
実は、かみ合わせの乱れは全身のバランスに影響を与え、頭痛や肩こり、消化不良など、思わぬ不調を引き起こすことがあるのです。
今回は、かみ合わせが悪いことで起こる可能性のある全身の不調と、その対策について解説します。
かみ合わせが悪いことで起こる全身の不調
かみ合わせが悪いと、以下のような症状が現れることがあります。
1. 頭痛・肩こり・首の痛み
かみ合わせが悪いと、顎の筋肉や関節に負担がかかり、筋肉の緊張が続きます。その結果、顎から首、肩にかけての筋肉がこわばり、慢性的な頭痛や肩こりを引き起こすことがあります。
2. 顎関節症
かみ合わせが乱れていると、顎関節に余計な負担がかかり、「顎が痛い」「口を開けると音がする」「口が開きにくい」といった症状が出ることがあります。これが 顎関節症 です。
3. 消化不良・胃腸の不調
食べ物をしっかり噛めないと、胃や腸に負担がかかり、消化不良を引き起こすことがあります。胃もたれや便秘、下痢などの症状が出ることもあります。
4. 姿勢の乱れ・腰痛
かみ合わせが悪いと、顎のバランスが崩れ、それを補おうと姿勢が悪くなることがあります。特に、片側で噛む癖があると、体の片側に負担がかかり、猫背や腰痛を引き起こす原因になります。
5. 睡眠の質の低下
かみ合わせが悪いと、無意識に 歯ぎしりや食いしばり をしてしまうことがあります。これが続くと、眠りが浅くなったり、顎の痛みで目が覚めたりすることがあり、結果として 睡眠の質が低下 してしまいます。
かみ合わせの乱れを改善する方法
かみ合わせの問題を放置すると、症状が悪化することもあるため、早めの対策が大切です。以下の方法を試してみましょう。
1. 歯科医院でのチェック・治療
かみ合わせが悪いと感じたら、まずは 歯科医院で診てもらう ことが重要です。歯並びや噛み合わせの状態を確認し、必要に応じて 矯正治療や噛み合わせ調整 を行うことで、症状の改善が期待できます。
2. 片側で噛む癖をやめる
片側ばかりで噛む癖があると、かみ合わせが偏ってしまうため、 左右バランスよく噛む ように意識しましょう。
3. 適切なマウスピースを使用する
夜間の歯ぎしりや食いしばりがある場合は、 ナイトガード(歯ぎしり防止用のマウスピース) を使用することで、顎への負担を軽減できます。歯科医院で自分に合ったマウスピースを作ってもらうのがおすすめです。
4. 顎のストレッチやマッサージをする
顎周りの筋肉が緊張すると、肩こりや頭痛が悪化しやすくなります。 顎のストレッチ や 首・肩のマッサージ を習慣化すると、筋肉の緊張をほぐしやすくなります。
5. 正しい姿勢を意識する
姿勢が悪いと、顎の位置がずれやすくなります。 デスクワークの際の姿勢 や 寝るときの枕の高さ にも注意し、体全体のバランスを整えるようにしましょう。
まとめ
かみ合わせの乱れは、 頭痛・肩こり・胃腸の不調・睡眠の質の低下 など、全身にさまざまな影響を及ぼします。
「たかがかみ合わせ」と軽視せず、 早めに歯科医院で相談することが大切 です。
普段の生活での 姿勢や噛み癖の改善、適切なケア を取り入れながら、健康的な噛み合わせを目指しましょう!
記事監修:歯科医師 まつおか歯科医院副院長 松岡夏紀