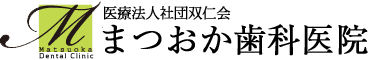食事をするとき、皆さんはどれくらい意識して「噛む」ことをしていますか?実は、よく噛むことはお口の健康だけでなく、脳にも良い影響を与えることがわかっています。今回は、噛むことと脳の関係性についてご紹介します。
噛むことで脳が活性化する!
食べ物を噛む動作は、単なる消化のための動きではありません。噛む刺激は、脳へ直接的に刺激を与え、活性化を促すといわれています。特に、前頭葉という「思考」「記憶」「判断」をつかさどる部分が活発になることが知られています。
ある研究では、よく噛んで食事をした後の方が、集中力や判断力が高まるという結果も報告されています。お子さまの学習能力や高齢者の認知機能の維持にも、「よく噛むこと」がカギになるかもしれません。
認知症予防にも期待
年齢を重ねると、歯を失ったり噛む力が弱くなったりすることで、脳への刺激が減少してしまいます。しかし、入れ歯やインプラントなどで噛む機能を補うことで、認知機能の低下を防ぐ効果があると考えられています。
また、「噛む回数が多い人ほど認知症のリスクが低い」といった調査結果もあり、お口の健康は脳の健康にもつながっていると言えます。
よく噛むための工夫
以下のような工夫をすることで、自然と「よく噛む」習慣が身につきます。
- 一口30回を目安に噛む
- 繊維質の多い野菜や噛み応えのある食材を選ぶ
- 姿勢を正して食事をする
- 食べる時間をしっかり確保する
まとめ:噛むことは“脳の体操”
「噛む」という毎日の何気ない動作が、脳の健康維持や認知症予防にもつながっているというのは驚きですよね。歯や噛み合わせに不安がある方は、ぜひ歯科でチェックを受けて、しっかり噛める環境を整えていきましょう。
l記事監修:歯科医師 まつおか歯科医院副院長 松岡夏紀