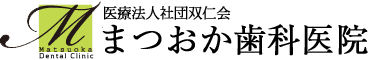こんにちは!2まつおか歯科医院副院長の松岡夏紀です。歯科治療を受ける際に欠かせない「麻酔」。実は上の歯と下の歯では、麻酔の効き方や持続時間に違いがあることをご存じでしょうか?
今回は、その理由をわかりやすくご紹介します。
1. 骨の硬さの違い
上の歯(上顎)は骨が比較的柔らかく、スポンジ状の構造をしています。そのため、麻酔薬が骨の中を通って歯の神経まで広がりやすく、効きやすく即効性があるのが特徴です。
一方で下の歯(下顎)は骨が非常に硬く、麻酔薬が浸透しにくいため、効き始めるまでに時間がかかることがあります。
2. 神経の走行の違い
上顎の歯は、それぞれの歯に神経が分かれているため、1本の歯に近い場所へ麻酔を打てば十分に効きます。
しかし下顎の奥歯は、太い「下歯槽神経」という大きな神経にまとめてつながっているため、神経の入り口(神経幹)に近い場所で麻酔を効かせる必要があるのです。そのため麻酔の方法が複雑になり、効きにくい場合があるのです。
3. 麻酔の持続時間の違い
骨の硬さや神経の構造の違いにより、下の歯の麻酔は効きにくい代わりに一度効き始めると持続時間が長い傾向があります。
逆に上の歯は効きやすい分、効果が切れるのも比較的早いのが特徴です。
まとめ
- 上の歯:効きやすく即効性があるが、効果は短め
- 下の歯:効きにくいが、効果が長持ちしやすい
これは骨の構造や神経の走り方が違うために起こる自然な現象です。
治療の際に「なかなか効かないな…」と感じても、歯科医師はしっかり効かせるために追加で麻酔をしたり、方法を変えたりしますのでご安心ください。
👉 当院では、できるだけ痛みを感じにくいように配慮した「無痛麻酔」を行っています。治療の際にご不安なことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
記事監修:歯科医師 まつおか歯科医院副院長 松岡夏紀