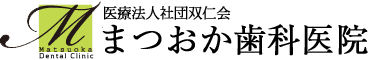こんにちは!まつおか歯科医院副院長の松岡夏紀です。「歯茎に小さなできものがある」「押すと膿が出てきた」──そんな経験はありませんか?
一見するとニキビのように見えるかもしれませんが、歯茎のできものは口腔内の健康状態を反映しているサインであることが多く、放置すると症状が悪化する恐れがあります。今回は、歯茎のできものに関して考えられる代表的な疾患とその治療法についてご紹介します。
歯茎にできものができる主な原因
1. 歯根嚢胞(しこんのうほう)
歯の根の先に膿がたまり、袋状の嚢胞となって歯茎に出口を作ることで、ぷくっとしたできものが現れます。虫歯や過去の神経治療が不十分な場合に起こることがあります。
2. フィステル(膿の出口)
歯の内部や歯根に炎症が起こり、膿がたまって外に排出されるためにできる小さな穴や膨らみです。膿が出ている間は痛みが落ち着くこともありますが、炎症の根本は治っていません。
3. 歯周病による膿瘍
歯周病が進行すると、歯と歯茎の間に膿がたまり、できもののように腫れることがあります。急に腫れて強い痛みを伴う場合もあります。
4. 良性の腫瘍やその他の病変
まれに良性の腫瘍や血豆のような病変が原因となることもあります。自己判断は難しいため、歯科での診断が必要です。
放置するとどうなる?
- 炎症が進み、歯を支える骨が溶けてしまう
- 膿が広がり、腫れや強い痛みを引き起こす
- 歯を残すことが難しくなる
見た目が小さくても、内部で大きな問題が進行していることがあるため、早めの受診が大切です。
治療方法
できものの原因によって治療は異なります。
- 根管治療(歯の神経の治療)
歯の根の中を清掃・消毒し、細菌感染を取り除きます。 - 歯周病治療
歯石やプラークを除去し、炎症を抑えます。重度の場合は外科的な処置が必要になることもあります。 - 切開・排膿
強い腫れや痛みがある場合、膿を排出して症状を和らげます。 - 外科処置や抜歯
歯を保存できない場合や嚢胞が大きい場合は、外科的な治療や抜歯が検討されます。
まとめ
歯茎にできものができるのは、体からの「注意信号」です。
「痛みがないから大丈夫」と放置せず、早めに歯科医院で診察を受けることが大切です。早期に対応すれば歯を残せる可能性も高まります。
当院では歯茎のできものの診断から治療まで丁寧に対応しております。気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。
記事監修:歯科医師 まつおか歯科医院副院長 松岡夏紀